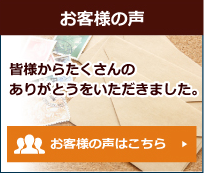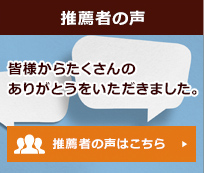相続法の改正の内容はどのようなものですか 弁護士 小林 塁
1.自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言は、名前のとおり自筆で作成する遺言です。
自費証書遺言が有効となる要件は、全文自署をすること、作成日付を書くこと、署名・押印です。
自筆で作成すればよいのですから、一見容易に作成できるはずですが、全文を自署しなければならないため、例えば不動産が多数あるような場合には、財産目録を記載するのが大変でした。
そこで、改正により、相続財産の特定に必要な事項(財産目録)については、自署ではなく、パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や、預金通帳の写しの添付で良いことになりました。
ただし、自署ではない財産目録の部分についても、各頁毎に署名・押印をしなければなりません。
2.遺言書保管法の制定
自筆証書遺言は、容易に作成できる反面、紛失してしまったり、遺言者が存命の間に相続人に見つかってしまうといったデメリットがありました。
そこで、遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が制定され、法務局が遺言を保管してくれる制度が創設されました。
3.配偶者居住権の創設
夫婦の一方がお亡くなりになったとき,他方配偶者は今までの住居に住み続けるのが通常だと思います。しかし、遺産の内容によっては,他方配偶者が遺産分割によって住居を取得すると,預金等の他の遺産を取得できなくて困ってしまうと言うこともあり得ます。他方で,配偶者としては家に住めればよく,所有権は子どもに渡して良いということもあります。
そこで,所有権とは異なる配偶者居住権(配偶者が長期間にわたり,居住が出来る権利)を創設し,遺言,遺産分割において柔軟な解決が可能となりました。
4.配偶者短期居住権の創設
配偶者短期居住権は,3の配偶者居住権とは異なり,遺産分割により居住建物の帰属が確定した日か又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日まで,配偶者は無償にて建物の居住を継続できるという権利です。
これにより,夫婦の一方が亡くなったときに,一定期間の間ではありますが,他方配偶者は問題なく建物への居住を継続することが出来ます。
5.遺留分制度に関する見直し
遺留分とは,遺言や贈与があっても相続人の残されるべき最低限の取り分を言います。
この遺留分額(遺留分侵害額)は一定の計算式のもとに算定されるのですが、計算のスタートとなる「遺留分を算定するための財産の価額」は,被相続人が相続開始のときに有した財産の価額に,被相続人が贈与した価額を加え,債務の全額を控除して計算されます。
この加算される「被相続人が贈与した価額」については、解釈上相続人に対する特別受益となるものは全て含まれるとされていました。
しかし、この金額を巡って熾烈な争いとなることがあり、特に相当程度昔のものですと、証拠もなく、「もらった、もらってない」の水掛け論になりがちでした。
そこで、改正により、加算される相続人に対する特別受益は、被相続人がお亡くなりになったときから、10年以内のものに限ることとされました。
なお、遺留分制度については、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)権から遺留分侵害額の請求権になるなどの法的性質の変更もなされています。
6.特別寄与料の制度
被相続人の生前、被相続人の財産の維持等に貢献した相続人は、遺産分割のさいに、寄与分として、その貢献に見合った遺産を取得することが出来ます。
しかし、相続人以外の親族は、いくら被相続人の生前に被相続人に尽くしたとしても、相続人でない以上遺産分割に参加することはできず、したがって、その寄与に見合うだけの金銭等を取得することが出来ませんでした。
しかし、改正により、被相続人に対して特別の寄与をした被相続人の親族は、特別の寄与に応じた金銭の支払請求を行うことができるようになりました。
相続法改正については、その他にも改正点がありますが、主要なものとしては以上となります。
関連記事はこちら
- 新潟大学経済学部「会計学特殊講義」の講師を担当しました 弁護士 五十嵐
- シニアカレッジの講師を担当しました 弁護士 五十嵐
- シニアカレッジの講師を担当しました 弁護士 五十嵐
- 草津温泉へ行く 弁護士 小林 塁
- 「認知症サポーター」について
- (裁判例紹介)福岡高等裁判所平成29年5月18日判決
- FP2級に合格しました! 弁護士 江畑博之
- 新潟市での「本人通知制度」の開始
- 民法(相続分野)改正の動き
- arikoの食卓 弁護士 小林 塁
- 水道が凍ると困りますね 弁護士 小林 塁
- テレビドラマの弁護士を見て思う事 弁護士 江幡 賢
- FP3級に合格しました! 弁護士 江畑 博之
- 農地(田畑)を相続する際の注意点
- 【3年連続】新潟県高齢者大学の講師を担当しました 弁護士 五十嵐 勇
- 姻族関係終了届とは? 弁護士 江幡 賢
- 預貯金が遺産分割の対象になる、の意味 弁護士 小林 塁
- 保険代理店様向けセミナーを開催しました!
- 節税目的の養子縁組は有効か? 弁護士 江幡 賢
- 「法定相続情報証明制度」が導入されます 弁護士 五十嵐 勇
- 新潟明訓中学校・高等学校へ行ってきました! 弁護士 五十嵐 勇
- イスを変えました
- muro式 9.5 「答え」
- 「こち亀」が終わる 弁護士 五十嵐 勇
- 【2年連続】新潟県高齢者大学の講師を担当しました!
- 新潟医療福祉カレッジへ行ってきました! 弁護士 五十嵐 勇
- 藤棚を見に行く 弁護士 小林 塁
- ドラマの中の弁護士 弁護士 五十嵐 勇
- 【5回連続】新潟明訓中学・高等学校へ行ってきました!
- 朝の雪かき 弁護士 五十嵐 勇
- 【2年連続】新津高校へ行ってきました!
- 2人の「エバタ」について 弁護士 江畑 博之
- 税理士の藤井さん 弁護士 小林 塁
- お雑煮を作ってみる 弁護士 小林 塁
- 相続無料相談会(12月19日)を開催しました!
- 保険代理店様向けセミナーを開催しました!
- 相続無料相談会(10月3日)を開催しました! 弁護士 五十嵐 勇
- 遺産分割調停をした場合にかかる期間 弁護士 江畑 博之
- 相続無料相談会(9月5日)を開催しました!
- 相続無料相談会(8月1日)を開催しました!
- 遺言書を作れば大丈夫? 弁護士 五十嵐 勇
- 新潟県高齢者大学の講師を担当しました! 弁護士 五十嵐 勇
- 新潟県立新潟北高校へ行ってきました! 弁護士 五十嵐 勇
- 新潟県立加茂高校へ行ってきました! 弁護士 五十嵐 勇
- 新潟県消防学校で講義を担当しました! 弁護士 五十嵐 勇
- 高齢者破産 弁護士 宮本 裕将
- 新潟県立新津高校へ行ってきました! 弁護士 五十嵐 勇
- 香港金融・投資視察 弁護士 宮本 裕将
- 新潟日報のコラムを執筆しました! 弁護士 五十嵐 勇
- 被相続人に子供さんがいないケースの相続