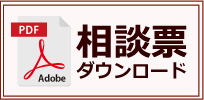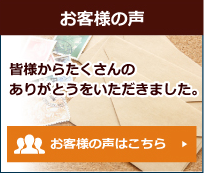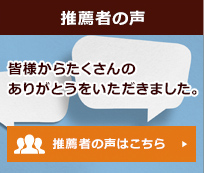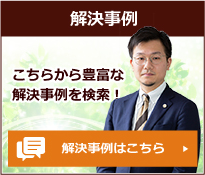養子の相続分について
質 問 先日、私の父が亡くなりました。母は父よりも前に亡くなっています。また、私には兄が一人いたのですが、数年前に亡くなっています。他に兄弟はいません。父には養子がいるのですが、実子(血縁関係のある子供)である私と養子の法律上の相続分に違いはありますか? 回 答 養子は、養子縁組した日から養親の法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子である嫡出子としての地位を取得します。つまり、実子と養子は 続きを読む
後見制度支援信託について
質 問 現在、私は母の成年後見人をしています。 実は、私が後見人に就任したのは、母が交通事故の被害に遭い、高次脳機能障害と診断されたためです。 この交通事故の処理が終わり、損害賠償金としてまとまったお金が保険会社から送金されるようです。 この話を家庭裁判所にしたら、「後見制度支援信託」の紹介をされたのですが、これはどういった制度なんでしょうか? 回 答 後見制度支援信託とは、被後見人 続きを読む
補助人の権限
質 問 補助人にはどのような権限が与えられますか? 回 答 保佐の場合と重複するのですが、同意権と取消権があります。 被補助人が一定の法律行為をする場合、補助人の同意が必要で、この同意を得ない場合には後から取り消すことができます。(民法16条1項、4項) [word_balloon id="5" position="R" size="M" balloon="talk" name_p 続きを読む
補助とは
質 問 成年後見制度の「補助」という類型について教えてください。 回 答 被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、 家庭裁判所より補助開始の審判を受けたものをいいます(民法15条、16条)。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" balloon="talk" name_position="under_av 続きを読む
保佐人の権限
質 問 保佐人が選任されると、どのような権限が与えられますか? 回 答 まず、「同意権」と「取消権」というものがあります。これは、被保佐人が民法13条1項所定の法律行為を行おうとする場合には、保佐人の同意が必要となるのですが、保佐人の同意がない場合、保佐人及び被保佐人は当該行為を取消すことができるのです(民法13条4項)。 [word_balloon id="5" position= 続きを読む
保佐人とは何ですか?
質 問 成年後見制度には、「保佐」という類型がありますが、これはどういったものでしょうか。 成年後見とどのように違うのでしょうか? 回 答 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所より保佐開始の審判を受けた場合をいいます(民法11条,12条)。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" bal 続きを読む
成年被後見人の死亡
質 問 成年後見人の業務はいつまで続くのでしょうか? もともと、認知症の父の自宅不動産を処分する目的があったのですが、この売却が終わったら、後見業務も終了するのでしょうか。 回 答 後見業務は目的を達成したからといって終了するものではなく、原則として本人が亡くなるまで業務は継続します。 [word_balloon id="5" position="R" size 続きを読む
成年後見業務の注意点
質 問 成年後見人の業務については、さきほどの質問で理解できました。 何か注意すべき点はありますか? 回 答 [word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon="talk" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="fa 続きを読む
成年後見人の仕事は?
質 問 認知症の父の成年後見人に就任する予定で、申立の準備をしたいと考えています。具体的にはどういった仕事をするのでしょうか。 回 答 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行う必要があり、これら事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(民法858条)。 [word_balloon 続きを読む
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)と特別受益について
質 問 父が死亡したのですが、生前、父は長女に全ての財産を相続させるという内容の遺言を残していました。 そのため、私は遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の内容証明を長女に送りました。 これに対して、長女は、私(長男)が20年前、住宅を建てるときに1000万円の贈与をうけていると主張して、遺留分を支払う必要はないと言ってきています。 どのように対応すればいいのでしょうか。 回 答 続きを読む